ソニーがミニLEDバックライトのRGB個別制御技術を用いた次世代ディスプレイシステムを開発したと発表しました。
ハイセンスは、100インチRGB-Mini LEDテレビを国内市場で発表し、製品化すると見られています。
レグザは、「RGB Mini LED液晶レグザ ZX1 series ZX1R」を、2025年12月5日に日本国内へ発売しました。
サムスンとTCLもRGB個別制御ミニLEDバックライトを搭載した液晶テレビの開発を進めています。
いよいよミニLEDバックライトは、RGB個別制御の時代に突入します!これは衝撃ですね!そのインパクトを見ていきましょう。
ソニーがLEDバックライトでRGB個別制御
ソニーは公式にRGB個別制御のミニLEDバックライトを搭載した次世代ディスプレイシステムを開発したと発表しました。
その冒頭部分は以下です。
ソニーは、高密度LEDバックライトをR (赤)、G (緑)、B (青) の色ごとに個別に制御可能なRGB独立駆動パネルを採用し、大画面化にも適したディスプレイシステムを開発しました。このパネルは、各色が独立して発光するため、色の純度が高く、映像をより鮮やかに広色域で再現できます。また、パネルの特性を最大限に引き出すために、ソニーが独自に開発した最新のバックライト制御技術を搭載しています。この技術により、大画面でも画面の隅々まで繊細な色合いと光の濃淡を忠実に再現します。
*ソニーのサイト(「独自の信号処理で高密度LEDバックライトをRGB各色で個別に制御可能な次世代ディスプレイシステムを開発」https://www.sony.co.jp/corporate/information/news/202503/25-010/ より)
RGB各色が独立して発光するため、色の純度が高く、DCI-P3 99%以上、ITU-R BT.2020 約90%の広色域をカバーできるとのこと(*試作機のスペックであり、今後同システムが搭載される製品のスペックでは必ずしもない)。
DCI-P3とBT.2020についてこちらの記事で紹介しています。
さらに、ソニーのプロフェッショナルモニターで実現している4000 cd/m2以上のピーク輝度を出すことができ、ソニーのディスプレイ機器史上最高のカラーボリュームを実現。
96ビットの高ビットレートで駆動しているため、細部まで精密に階調を制御可能。
制御用プロセッサーにおいては、ソニーとの長期的戦略パートナーであるMediaTek Inc.と共同開発を行ったほか、LED部においてもSanan Optoelectronics Co., Ltd.と共同開発、ローム株式会社とLED駆動ICについて共同開発。
以上がSONYの公式発表の要点です。これのどこが衝撃的なのか?
最近普及し、急激に液晶テレビの高画質化に大きく貢献したミニLEDバックライト技術の進化系であり、製品化・普及の可能性として高いポテンシャルがあることに注目です!
「広色域化」「高ピーク輝度化」「より緻密な階調制御」は、ディスプレイの画質の基本要素を向上させることで、もっとも重要な部分です。
色域だけを比較すると、一見現在の量子ドットを用いたテレビと同じあるいはわずかに劣ると感じる方もいるかもしれません。しかし、それは誤解です。
なぜなら2次元の色度図上で表される色域は、あくまでもある輝度(ディスプレイの明るさ)における色表示範囲を示したもので、低輝度から高輝度までの実際にテレビで表示されるあらゆる色の範囲を示したものではありません。
本当にテレビで表示できる色範囲を示すものはカラーボリューム(色空間)で、3次元的に示す必要があります。このカラーボリューム(色空間)において、「ソニーのディスプレイ機器史上最高のカラーボリュームを実現」と言っているわけです。
つまり、これまでのミニLEDテレビだけでなく、有機ELテレビ(WOLED)、QD-OLEDよりも広いカラーボリュームということになります!これはすごいです!
なぜ量子ドットを上回るカラーボリュームが実現できる?
これまでは、量子ドットを用いたテレビがもっとも広色域とされています。量子ドットは、青色光を吸収し、スペクトル幅が狭い緑色光または赤色光を放出することができるためです。
なぜ量子ドットを用いたテレビよりも、RGB独立制御のミニLEDバックライトを用いたこのシステムの方が広大なカラーボリュームを実現できるのでしょうか?
ソニーの公式発表では、RGB各色のLEDの発光スペクトルに関する情報は開示されていないため、これらによる広色域化への貢献はわかりません。
しかし、RGB独立制御という点からわかることは、「青色LED+量子ドットシート」というシステムよりも、カラーボリュームの向上に有利であるということです。
現在主流の量子ドット搭載テレビは、「青色LED+量子ドットシート」というシステムになっています。このシステムでは、青色を発光させた時に、必ず緑色と赤色も放出され、全体として白色を作り出します。
そして表示させる映像に合わせて、各色のサブピクセルを、カラーフィルターと液晶セルによって調光しています。しかし、現状の製品では、量子ドットの緑色と赤色の発光スペクトルが理想的なものよりも広がりがあり、カラーフィルターを通過しても混色がわずかにあります。これがカラーボリュームを制限する要因の1つになります。
一方、RGB独立制御のミニLEDバックライトならば、各色を必要に応じて調光すればよく、混色も最小限に抑えられ、さらに各色の中の特定の色を強烈に強く発光させることも可能です。原理的に優れていることが明らかです。
MicroLEDディスプレイが、究極のディスプレイと呼ばれることがありますが、RGB独立制御としてさらにミニLEDの個数を増やしていけば、仕組み的にもどんどんMicroLEDに近づいていきます。
またMicroLEDディスプレイに比べると、ミニLEDテレビはカラーフィルターと液晶による調光の仕組みがあるため、広色域化と調光(階調性)という点で有利と言えなくもありません。
RGB独立制御ミニLEDテレビは普及するか?
どんなに優れた技術を搭載した製品でも、普及しなければ意味がありません。ソニーは、ミニLEDバックライトを搭載したテレビを全ラインアップのフラッグシップに位置づけています。
2024年モデルでは、BRAVIA 9がフラッグシップで、正直なところかなり高価です。
RGB独立制御のミニLEDテレビは、このBRAVIA 9の後継機種、あるいはさらに上の機種として製品化される可能性が高く、その価格も当初は高いでしょう。
期待したい点は、ミニLEDは半導体製品であり、その価格は生産量が桁違いに増えると、桁違いに下がる可能性が高いことです。これまでのLEDの価格推移を見てもそのような傾向があります。
その他に実装技術や制御用ICなども関係していますが、これらも参入メーカーが増えて市場が大きくなれば低価格化が期待できます。
実際、ここ数年のミニLEDバックライトは、使用するミニLEDの個数が急激に増えながらも、急激にコストダウンが進み、ミニLEDテレビの性能も向上しました。そのトレンドがRGB個別制御のミニLEDテレビにおいても続くと予想されます。
前述のように、すべてをソニーが独自開発するのではなく、MediaTek Inc.、Sanan Optoelectronics Co., Ltd.、ローム株式会社と共同開発するという点も合理的な動向です。
さらにハイセンス、サムスンなどもそれぞれのパートナーと共同開発パートナーと製品化を進めていけば、大きなトレンドとなるでしょう。
ある程度のコストまで下がれば、「青色LED+量子ドット」システムにはかなりの逆風となるでしょう。
ソニーはバックライト技術を重視してきた
ソニーの公式発表に以下のような部分があります。
当社は、2004年に世界初のRGB一括駆動LEDバックライト搭載液晶テレビを開発しました。それ以来、バックライト制御の精度向上に継続的に取り組み、その経験からLED素子の特性を熟知しています。本ディスプレイシステムの開発においても、独自のバックライト制御技術がパネルの性能を最大限に引き出すことに貢献しています。
*ソニーのサイト(「独自の信号処理で高密度LEDバックライトをRGB各色で個別に制御可能な次世代ディスプレイシステムを開発」https://www.sony.co.jp/corporate/information/news/202503/25-010/ より)
実際、ソニーは「バックライトマスタードライブ Backlight Master Drive」として、液晶パネル直下に多数のLEDを配置し、それらを個別制御する技術を業界をリードして開発してきました。
さらに振り返れば、2004年にQUALIA(クオリア)ブランドのテレビに、RGB一括駆動のバックライトを搭載しています。
その後は、青色LEDに蛍光体を組み合わせたLEDが用いられてきましたが、ついにRGBのLEDを搭載し、さらには個別制御に発展させているわけです。
このような技術の蓄積がソニーの強みです。さらにマスターモニターなどの映像制作者向けのプロ用機器の開発、映画などのコンテンツ制作者としての経験が大きく、ディスプレイの進むべき方向を熟知しています。
RGB Mini LED液晶レグザ発売
レグザから、「RGB Mini LED液晶レグザ ZX1 series ZX1R」が、2025年12月5日に日本国内へ発売されました。
インチサイズは116V型、価格は660万円(税込み)です。とても多くの台数が売れるような価格とサイズではありませんが、RGB Mini LEDテレビのポテンシャルを考えれば、まずは1,000万円を大きく下回る価格で発売されたことに驚きを感じます。
これならば、今後数年で200万円以下まで下がりそうですし、より小さなインチサイズの製品が出るようであれば、100万円以下となるのもそれほど遠い未来ではなさそうです。
注目の色域については、75Z970Nの110%の広色域化を実現と紹介されています。
単純な2次元の広色域化だけでなく、3次元のカラーボリュームが拡大されているわけですが、データは公表されていないため、詳細は確認できません。
QD-OLED搭載テレビを見ると、カラーボリュームの拡大はすぐにわかるので、RGB Mini LEDテレビにおいても表示映像を見ればすぐに体感できるでしょう。
ハイセンスが100インチRGB-Mini LEDテレビを発表
ハイセンスは、100インチRGB-Mini LEDテレビを中国国内市場向けに発表しました。赤・緑・青の3色の光源を独立して調光・調色することが可能です。
テレビの色域カバー率を97% BT.2020とのことですので、かなりの広色域です。
ハイセンス以外にも、2025年にはサムスンやTCLがRGB-LED方式の製品を発表する見込みです。
ミニLEDテレビは主流になる?
2024年の日本国内のテレビ市場では、有機ELテレビの販売は低迷し、ミニLEDテレビは勢いを増しました。これからの高価格帯の上位機種としては、ミニLEDテレビが主流となるのでしょうか?
有機ELテレビは、発売当初は輝度の低さ、焼き付きなどの弱点を指摘されていましたが、その後の研究開発により、かなり改善され、主要テレビメーカーのフラッグシップモデルとして販売されるまでになりました。
しかし、液晶テレビもミニLEDバックライトの搭載により、弱点とされたコントラストがかなり改善され、画質面で有機ELテレビと比べても遜色ない水準に達しています。
ミニLEDバックライトは、猛烈なコストダウンが進み、ミニLEDテレビの価格も下がってきました。それに比べると、有機ELテレビのテレビはパネルレベルで大きな技術革新があり、その分コストダウンが進まず、有機ELテレビの価格も高止まりしている印象を受けます。
ミニLEDテレビでは、使用するミニLEDの個数を大幅に増やしても、価格をそれなりに抑えることに成功しているようです。さらに本記事で紹介したようなRGB独立制御なども普及価格帯の機種に搭載されるようになれば、画質面でも有機ELを上回るものがより安い価格で登場するかもしれません。
ソニーでは普及価格帯のミニLEDテレビBRAVIA 7が売れ筋です!高画質を楽しめます!
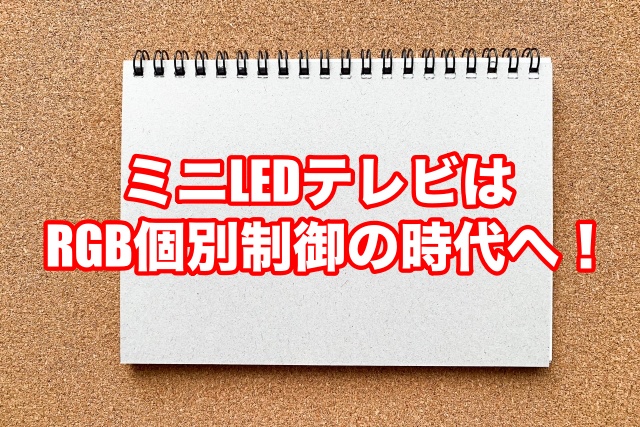
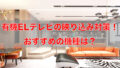
コメント